
平安~室町時代って、何だか色々ともやもやすることがありませんか?ぼくはありました。
今回は、そんな中学生のころにぼくがもやもやしたことを、今の知識で解説してみます。
この当時のあれこれ
政治を行う人の資格
このころの社会では、現代とは比べものにならないほど「血筋(家柄)」が重視されていました。
とくに、天皇の血を引く人(皇族やその子孫)は「貴種(きしゅ)」と呼ばれ、政治のリーダーとしてふさわしいと考えられていたのです。
逆に言えば、どれだけ実力があっても、貴種でなければ「正統なリーダー」として認められにくく、人もついてこなかったのです。
源氏・平氏とは
平氏や源氏というのは、もともと天皇の子どもたちが、皇族から外れて臣下になったときに名乗った名字です。
昔の天皇にはたくさんの子どもがいたので、位の低い子どもたちは「皇族」から外れ、「平」「源」などの姓を与えられて臣籍降下しました。
ただし、「平氏」「源氏」とひとことで言っても、どの天皇の子孫かによって、たとえば清和源氏、嵯峨源氏、桓武平氏など、さまざまな系統に分かれています。
つまり、「源氏」「平氏」はひとつのまとまった一族というわけではなく、必ずしも敵対していたり、逆に仲が良かったりするわけでもありません。

ぼくは、「源氏VS平氏」=いつも戦ってるライバル一族、みたいに思ってましたよ!
さらに、同じ清和源氏の中でも、拠点とする地域によって河内源氏・甲斐源氏などに分かれていきます。また、その土地の名前をそのまま名字にすることもありました。
実際、戦国時代の武田信玄は、甲斐源氏の流れをくむ人です。

ややこしいですよね!
源頼朝は、清和源氏の中でも河内源氏の出身です。一方、平清盛は桓武天皇の血を引く桓武平氏の流れをくむ、伊勢平氏にあたります。
平安時代の後半に「平氏と源氏の戦い」とよく言われますが、正確には「伊勢平氏と河内源氏の争い」なんですね。
この両者は、どちらも天皇に近い血筋を持ち、「貴種(きしゅ)=高貴な家柄の人」とみなされていました。
河内源氏についてもう少し深堀り
河内源氏は、平安時代に活躍した名門の武士の家系です。特に有名なのが、前九年の役や後三年の役という、東北地方の戦いでの大活躍です。
中でも、源義家という人物は、後三年の役での戦いぶりが伝説的で、「八幡太郎」という通称でも知られています。
義家は戦の強さだけでなく、人柄の面でも武士の理想像(=武士の鑑)とされていました。たとえば、後三年の役では、朝廷から「これは私的な戦争だ」として報酬が出なかったのに、義家は自分の財産を使って部下に報酬を出したというエピソードがあります。
こうした義家の姿は、当時の武士たちの間で絶大な尊敬を集めました。
義家の子孫たちは各地で活躍し、その名声は時代を超えて受け継がれていきます。
たとえば──
- 室町幕府を開いた足利尊氏は、河内源氏の出身です。
- 江戸幕府を開いた徳川家康も、自らの家系図を河内源氏につなげて「源氏の正統な子孫」と主張しました。(本当は違うらしいですが)
これだけ長い時代にわたって影響を与えていたことからも、河内源氏のネームバリューのすさまじさがよくわかると思います。
武士たちにとって、「河内源氏の血を引いている」というのは、正統なリーダーとしての資格を示すブランドのようなものだったのです。
もやもやの答え
なぜ、源氏は「氏」なのに、平家は「家」なのか?
「平氏」というのは、天皇の子孫が臣籍降下して名乗った一族全体を指す名前です。
一方で、「平家」という言葉は、平清盛を中心とする一門のことを指しています。
つまり「平家」とは、単なる血筋の呼び名ではなく、「清盛を中心とした一族の政治的・社会的なまとまり(家政・体制)」を含んだ言葉なのです。
清盛一門が貴族社会に入り込み、実際に朝廷での政治を動かすようになったことで、「家」としてのまとまりが強く意識され、「平家」と呼ばれるようになりました。
一方の源氏には、「源家」という呼び名はあまり使われません。
それは、源氏が政権を取ったあとに幕府という新しい政治制度を作ったことで、「源氏政権=幕府」というはっきりしたイメージができ、わざわざ一門を家でくくる必要がなかったからかもしれません。

ちなみに、歴史的に見れば、「平家」は貴族政治から武士の政治への橋渡しをした重要な存在です。平清盛がいなければ、源氏による幕府も成功しなかったかもしれません。
日本の歴史では「源氏が正義」「平家は悪」という図式で語られがちです。しかし、実際には、平家はとても先進的なことをしていて、海上貿易・外交・人材登用など、武士政権の土台となるような取り組みもしていました。
歴史を深く学ぶと、平家は「敗者」ではあっても「悪者」ではなかったことがわかります。平家の評価が変わると、源平の対立ももっと多面的に見えるようになりますね。
なぜ、源平の合戦で流罪だった頼朝が大将になれたのか?
これは、頼朝の家格で説明がつきます。
先ほどの項で説明した通り、頼朝は河内源氏の出身で、しかも父・源義朝は当時の武士のリーダー的存在でした。また、頼朝自身も、その正統な後継ぎでした。
たとえ流罪になっていても、「源氏の正統な後継ぎ」としての格・血筋の強さがあったため、各地の武士たちは「源氏の大将は頼朝しかいない」と考えたのです。だから、いざ平氏を倒そうという流れになったとき、自然と頼朝が旗頭になりました。
なぜ、北条氏は自分が将軍にならずに執権政治を行ったのか?
一言で言えば、格が足りなかったからです
河内源氏の項で述べた通り、以前も説明したとおり、源頼朝は、河内源氏という名門の出身で、武士の中でも群を抜いた「スーパーサラブレッド」でした。しかも、鎌倉幕府を開いたという実績もあり、家柄・能力ともに他の追随を許さない存在でした。
それに対して北条氏は、たしかに桓武平氏の流れを汲むとされる家系ではありますが、実際には伊豆の地方豪族にすぎません。源頼朝と比べれば、その「格の差」は歴然だったのです。
さらに悪条件だったのは、平家の記憶がまだ人々に強く残っていたことです。
北条氏が将軍になれば、「格が低いくせにまた平氏が権力を好き勝手に使い始めたぞ」と思われた可能性が高いでしょう。実際、執権政治を始めたころから、「北条氏の専横」という批判はすでに出ていました。
そうした背景もあり、北条氏は「自分たちは将軍にはならず、あくまで源氏将軍を支える」という立場を貫くことで、政権に正統性を持たせようとしたのです。
なぜ、後鳥羽上皇は源氏が途絶えたタイミングで承久の乱を起こしたのか?
それは、後鳥羽上皇が、「今こそ幕府を倒せる」と判断したからです。
北条氏が将軍にならなかった理由と同じで、北条氏は「格」が高い家柄ではなかったため、後鳥羽上皇は「御家人たちも、北条のような家に従うとは思えない」と考えたのです。実際、北条氏は地方の豪族出身で、源頼朝のような名門の出ではありません。ですから、上皇がそう判断したのも無理はない面があります。
ところが――
幕府側は、頼朝の妻である北条政子が「あなたたちは、頼朝様から数々の恩を受けたでしょう。今こそ、そのご恩に報いるときです!」という有名な演説を行い、御家人たちの心を一つにまとめます。
御家人の結束を図るために、源頼朝の権威を利用しようと考えた発想自体が、まず非常に優れていると思います。さらに、その役目を最も効果的に果たせる人物として、北条政子が自ら演説を行った点に、北条氏のバランス感覚のよさがよく表れていると感じます。
実際、この言葉に動かされた御家人たちは団結し、結果、幕府側が勝利。後鳥羽上皇は隠岐に流されることになりました。

北条氏は「源氏から政権を奪った一族」と見られがちです。しかし、実際には、
- 執権政治という新しい政体をつくった
- 御成敗式目という武士の法律を整えた
- 政子の演説に見られるようなバランス感覚
という点から見ても、非常に高い政治能力をもった一族だったと言えると思います。
そう考えると、北条氏はやはり、現在の日本の政治文化や仕組みを形づくるうえで欠かせない存在だったのではないでしょうか。
源氏、平氏、いつの間にかどっちも名前を聞かなくなるけど、どこに行ったのか?
源氏や平氏の名前は、ある時期を境にあまり聞かなくなりますが、どこかへ消えたわけではありません。実際、その後の有名な武将たちの多くが、源氏や平氏の血を継いでいるとされていますし、今でも日本各地にその子孫はたくさんいると思われます。
では、なぜ名前をあまり聞かなくなったのかというと、「○○源氏」「○○平氏」のように分かれが複雑になったことに加え、時代が進むにつれて「天皇とのつながり」よりも「土地とのつながり」の方が重視されるようになったためです。
その結果、人々は土地の名前を名字にするようになり、「源氏」「平氏」と名乗る機会が自然と少なくなっていったのです。

ちなみに、うちは母方が平氏の流れだそうです。
祖母が家系図を何度も見せて説明してくれたのですが、火事で焼けてしまいました。
当時はあまり興味がなくて聞き流してしまっていたのですが、今になって、ちゃんと見ておけばよかったなと後悔しています。
おわりに

平安時代から室町時代にかけての歴史は、結果の羅列になりがちで、とっつきづらい部分があります。
でも、源氏や平氏、北条氏のような有名な一族も、それぞれ背景や事情があって動いていたことを知ると、歴史がぐっと身近に感じられると思います。
この記事が、歴史のもやもやを解消し、歴史の「流れ」や「背景」を意識しながら学ぶきっかけになれば嬉しいです。

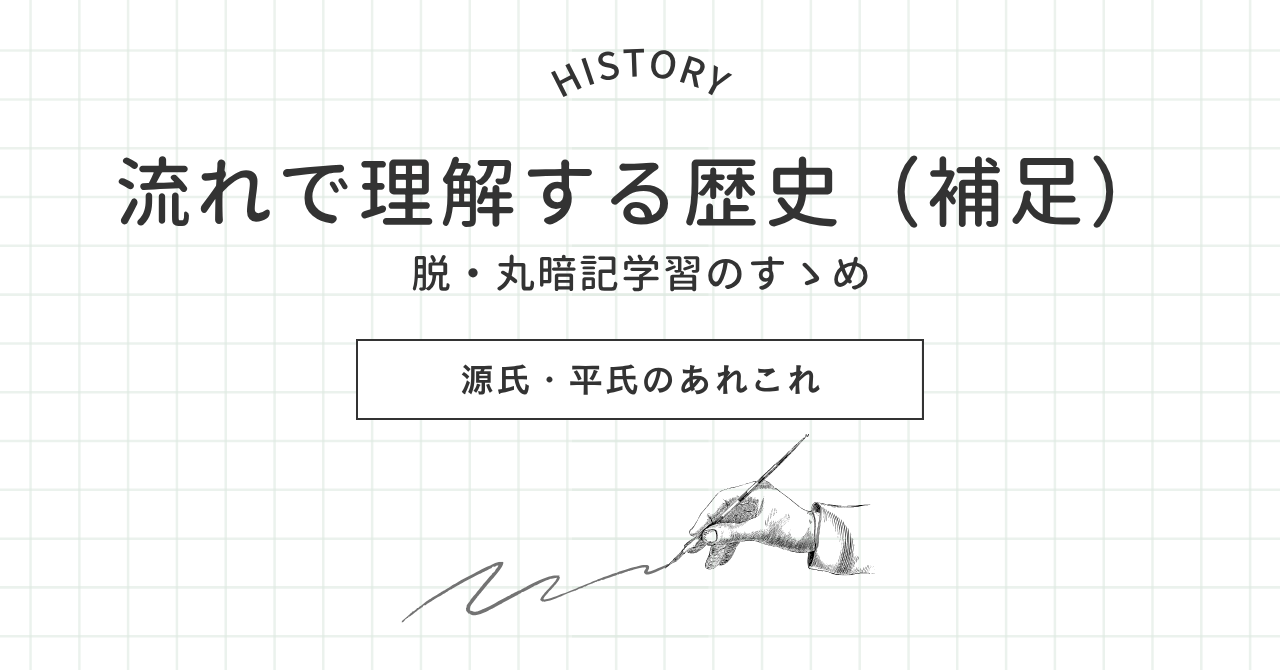


コメント