数学のテストで因数分解の問題を見たとき、手が止まってしまうことはありませんか?
「どの公式を使えばいいか分からない」
「ひらめきがないと解けない気がする」
塾で多くの生徒を見てきましたが、そう悩む子には共通点があります。
それは、「公式以外の解き方があるのではないか」と疑っていることです。
でも、実際は、因数分解には公式以外の解き方はなく、突き詰めれば「5つの選択肢から選ぶだけの照合作業」です。
この記事では、因数分解の本当の意味と、なぜ「公式以外は考えなくていい」と言い切れるのか、その戦略的な理由をお伝えします。
因数分解って何?
なぜわざわざ「かけ算の形」にするの?
たとえば、
\(a+b=0\)
という式があっても、\(a\)、\(b\)がいくつかはわかりませんが
\(a \times b = 0\)
という式があれば、かけて 0 になる数字は 0 しかないです。
だから、\(a\)、\(b\)のどちらか1つは 0 であるということがわかります。
このように、足し算よりかけ算の方が、式を検討しやすいのです。
因数分解とは、式を考えやすくするための整理の方法だと思ってください。
因数分解の仕組みを具体例で確認しよう
因数って何?
数や式をかけ算の形に直したときの要素のことを因数と言います。
いくつか具体例を見てみましょう。
- \(8=2 \times 4\)
⇒\(2\)と\(4\)は\(8\)の因数 - \(xy=x \times y\)
⇒\(x\)と\(y\)は\(xy\)の因数 - \((x+1)(x+2)=(x+1) \times (x+2)\)
⇒\((x+1)\)と\((x+2)\)は\((x+1)(x+2)\)の因数
では、因数の意味がわかったところで、次は因数分解とは何かを見ていきましょう。
因数分解は「かけ算のカタマリ」を作ること
一言で言うと展開の逆です。
たとえば、\((x+1)(x+2)\)を展開すると\(x^2+2x+3\)になりますよね。
これを、逆に
\(x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2)\)
と戻すことを、因数分解と呼びます。
因数分解とは、多項式(足し算、引き算で項がつながる式)をかけ算だけの式に変形する操作のことなんです。

「カッコの中に足し算があるじゃないか」
と思われる方がいるかもしれません。
しかし、カッコの中はひとかたまりとして見るが数学のルールなので、カッコ内の足し算、引き算はあっても構いません。
文字と数字で計算できないので、そのまま残っているだけと考えてください。
因数分解する問題はパターンの確認作業
因数分解の定義は「展開の逆」ですが、具体的にテスト中に何をやるのかというと、実は次の2ステップだけです。
- 式が「展開公式の結果」の形になっていないか確認
- なっていた場合、公式通りに式を変形
色々と学ぶので、途中、何をしているのかがわからなくなってしまうかもしれません。
でも、実際にやっていることは「展開公式の結果」の形になっているかの確認作業なんです。

どこに注目して確認していけばよいかは、次の記事から説明していきます。
因数分解の武器はたったの5つだけ
ここで一番大切なことをお伝えします。
テストで出てくる因数分解は、100%『公式のどれか』に当てはまるように作られています。
世の中には、公式で因数分解できない数式はたくさんあって、むしろ公式で因数分解できる数式はごくわずかな例外です。
しかし、問題として出題されるのは、そのごくわずかの例外の数式だけなんです。
自分の知らない魔法のような解き方があるんじゃないか、と不安になる必要はありません。
『公式のどれかには絶対にある』と信じて、消去法でチェックしていく。
これが、手が止まらない人の本当の思考法です。
因数分解の公式には、次の5つがあります。
- 共通因数でくくる
\(ma+mb=m(a+b)\) - 和と積の公式
\(x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)\) - 2乗の公式(プラス)
\(x^2+2ax+a^2=(x+a)^2\) - 2乗の公式(マイナス)
\(x^2-2ax+a^2=(x-a)^2\) - 2乗-2乗の公式
\(x^2-a^2=(x+a)(x-a)\)
つまり、因数分解の問題では、この5つの公式のどれに当てはまるかを考えているだけなのです。
おわりに
お疲れさまでした。
因数分解は、決して「センス」や「ひらめき」が必要なものではありません。
「この形なら、この公式」という、徹底した確認作業の世界です。
選択肢は5つ。
そして、実はその5つをチェックする「最も効率的な順番」が存在します。
次回からは、その戦略の第一歩、「第1回:共通因数」について解説します。
すべての因数分解において、真っ先に確認すべき「絶対の儀式」です。
ここをマスターするだけで、計算ミスと迷いは劇的に減りますよ。
一緒にがんばりましょう。
【関連記事】
- 次の記事を読まれる方はこちら
因数分解の公式の1つめ、「共通因数でくくる」タイプの因数分解です。
すべての因数分解は、まず共通因数がないかを確認するところから始まります。
共通因数とは何か、具体的な因数分解の方法、よくあるミスについてまとめているので、ぜひ読んでみてください。
👉共通因数でくくる因数分解のコツ!元塾講師が教える「ミスゼロ」の3ステップ

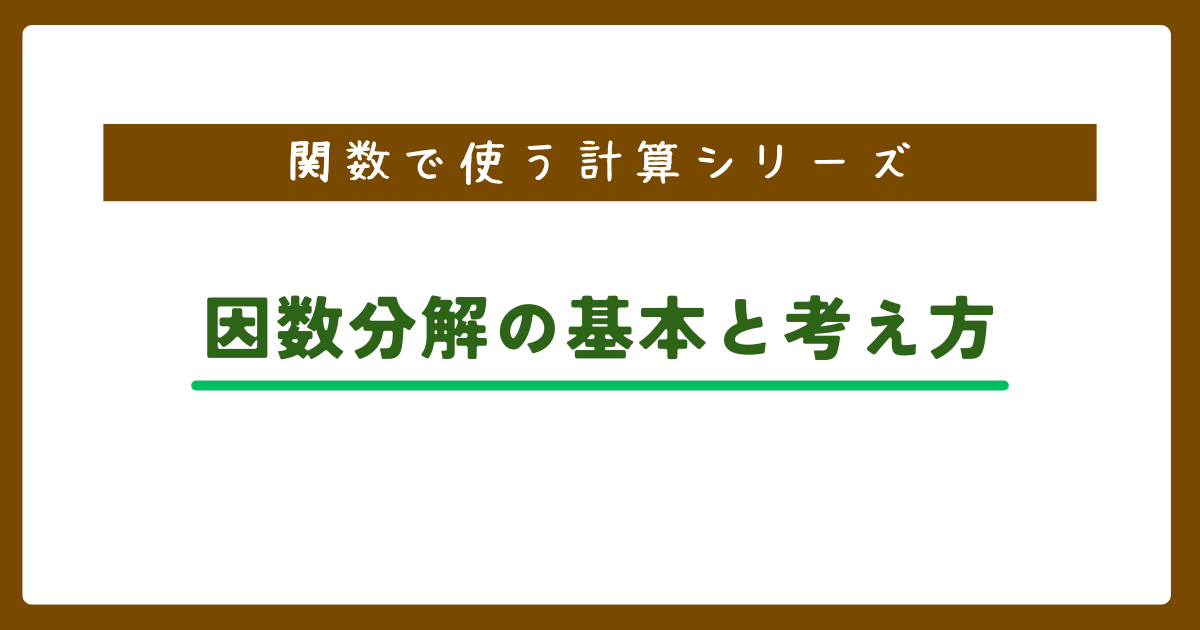
コメント