かけて〇、足して△になる数字を探す。因数分解で一番お世話になる公式ですが、意外と苦戦している人も多いのではないでしょうか?
特に数字が大きくなってくると、『ペアが全然見つからない!』とパズルのように迷子になってしまいがちです。
そこでこの記事では、和と積の公式の『基本の使い方』はもちろん、ぼくが塾講師時代に教えていた『一瞬で数字を絞り込むプロの技』までをセットで解説します。
基礎からしっかり固めたい人も、計算スピードを劇的に上げたい人も、ぜひ参考にしてください。これを読めば、もう数字探しで迷うことはなくなりますよ!」
和と積の公式ってどうやって使えばいい?
「因数分解といえばこれ」みたいな公式です。
この公式は、
\(x^2+○x+△\)
のような形の式に使います。
具体的には、次の手順で使えるかどうか確認できます。
(式中の赤字部分に注目してください)

ちょっと先の話ですが、他の公式でも、まず見るべきは定数項です。
だから、因数分解をするときは、次の順で考える習慣をつけてください。
- 共通因数がないか確認
- 定数項の確認
具体例で和と積の公式を確認してみよう
例1
\(x^2+4x+3\)
- 定数項\(3\)
かけて\(3\)になる数字の組み合わせは、
\((1,3),(-1,-3)\) - \(x\)の係数\(4\)
1.のうち足して\(4\)になる組み合わせは、
\((1,3)\) - 公式\(x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)\)において
\(a=1,b=3\)とわかるので
(\(a\)と\(b\)が逆でもいいです)
\(x^2+4x+3=(x+1)(x+3)\)
例2
\(x^2-6x+8\)
- 定数項\(8\)
かけて\(8\)になる数字の組み合わせは、
\((1,8),(2,4),(-1,-8),(-2,-4)\) - \(x\)の係数\(-6\)
1.のうち足して\(-6\)になる組み合わせは、
\((-2,-4)\) - \(a=-2,b=-4\)を公式に当てはめると
\(x^2-6x+8=(x-2)(x-4)\)
例3
\(x^2-2x-24\)
- 定数項\(-24\)
かけて\(-24\)になる数字の組み合わせは、
\((1,-24),(2,-12),(3,-8),(4,-6),(6,-4),(8,-3),(12,-2),(24,-1)\) - \(x\)の係数\(-2\)
1.のうち足して\(-2\)になる組み合わせは、
\((4,-6)\) - \(a=4,b=-6\)を公式に当てはめると
\(x^2-2x-24=(x+4)(x-6)\)

定数項が大きくなってくると、その分書き出す候補も増えていきます。
そんなときは、候補の絞り込みを楽にできる次で説明する方法を試してみてください。
候補をぐっと絞る!2つの数字の探し方
基本は全部書き出せば見つかりますが、それだと時間がかかってしまいます。
そこで、次のように2つの数の数字と符号をわけて探すとすっきり考えることができます。
言葉だけだとわかりづらいと思うので、例で確認してみましょう。
例4
\(x^2-17x+72\)
- 【数字を考える】
- 【定数項の符号】
\(x^2-17x \color{red}{+} 72\)
⇒2数を足すと、\(x\)の係数の数字の\(17\) - 【\(x\)の係数の数字】
\(x^2-\color{red}{17}x +72\)
\(x\)の係数の数字部分が\(17\)
定数項の\(72\)と比べると、値は小さい
⇒2数は近い数字 - 【数字の予想】
かけて\(72\)、足して\(17\)の近い数字
⇒\(8 \times 9,4 \times18\)あたり?
⇒\(8+9=17\)なので、数字の組み合わせは\(8,9\)
- 【定数項の符号】
- 【符号を考える】
\(x^2 \color{-}17x+72\)
\(x\)の係数が負の数
⇒2数はともに負の数
⇒\((-8,-9)\)が因数分解できる組み合わせ
よって
\(x^2-17x+72=(x-8)(x-9)\)
例5
\(x^2+30x-64\)
- 【数字を考える】
- 【定数項の符号】
\(x^2+30x \color{red}{-} 64\)
⇒2数を引くと、\(x\)の係数の数字の\(30\) - 【\(x\)の係数の数字】
\(x^2+\color{red}{30}x -64\)
\(x\)の係数の数字部分が\(30\)
定数項の\(64\)と比べると、値は大きい
⇒2数は遠い数字 - 【数字の予想】
かけて\(64\)、引いて\(30\)の近い数字
⇒\(1 \times 64,2 \times 32\)あたり?
⇒\(32-2=30\)なので、数字の組み合わせは\(2,32\)
- 【定数項の符号】
- 【符号を考える】
\(x^2 \color{+}30x-64\)
\(x\)の係数が正の数
⇒2数のうち、大きい方が正の数
⇒\((-2,32)\)が因数分解できる組み合わせ
よって
\(x^2+30x-64=(x-2)(x+32)\)

慣れるまでが大変ですが、慣れてしまえば数字の組み合わせを見つけるのがぐっと速くなりますよ。
おわりに
今回は、”かけて◯、足して△”の公式の基本と計算の工夫を紹介しました。
塾の講師をしていたころの話ですが、この考え方は、数学が得意な生徒には公式の導入時にあわせて説明することが多く、苦手な生徒にはテスト前の演習時などに補足的に伝えていました。
人によっては、候補を全部書き出した方がはやいし正確という人もいます。
他にも自分なりの判断ポイントはあります。
しかし、状況に応じて使い分けているため、この記事では割愛しています。
塾などであれば、個人の進度に合わせてアドバイスできるのが強みですね。
どれが正しい方法というものでもないです。
だから、「自分が使いやすい方法」を見つけることが一番大事ですよ。
【関連記事】
- 次の記事を読まれる方はこちら
使える式は限られるけれど、気づくとすぐに因数分解できる「2乗の公式」。
式のどの部分に注目して、どの順番で確認すればよいか、具体例を用いて詳しく解説しています。
和と積の公式と、2乗の公式の使い分けができれば、因数分解のかなりの部分がわかってくると思います。
ぜひ読んでみてください。
👉因数分解「2乗の公式」の見抜き方!ミスを防ぐ確認手順 - 演習問題を解きたい方はこちら
解説を読んで「なるほど!」と思ったら、次は実際に手を動かして、その感覚を脳に刻み込む番です。
今回学んだ「遠い・近い」のコツを使いこなせれば、大きな数字の因数分解もパズルのようにスラスラ解けるようになりますよ。
全6問のステップアップ演習を用意したので、さっそく「最速の数字探し」を体感してみてください!
👉和と積の組み合わせを最速で出す裏ワザの演習

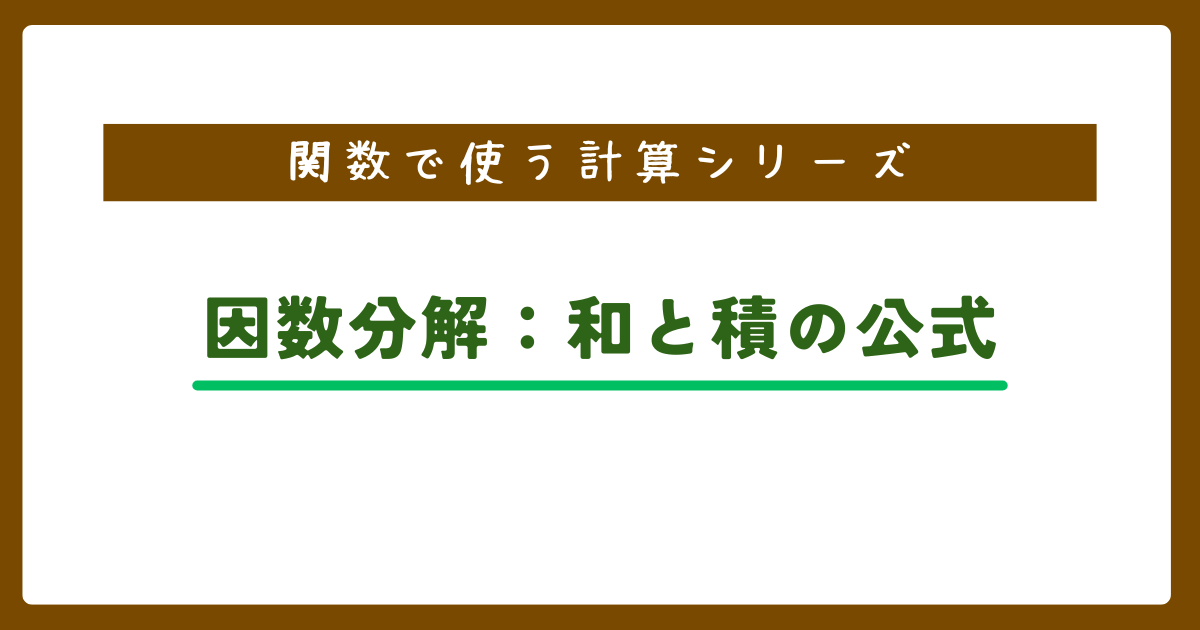
コメント