「\(x\)、\(y\)、どうやって計算したらいいんだっけ?」
そんなこと思ったことないですか?
関数で\(x\)や\(y\)の値を計算したいときは、基本的に関数の式を使います。
これは、どんな関数であっても共通です。
この記事では、関数の式を使って\(x\)、\(y\)を計算する基本の考え方を、例を通してわかりやすく整理します。
どうやって関数の式から\(x,y\)を計算したらいい?
\(x,y\)は関数の式に代入して計算!
なぜ代入で\(x,y\)を求められるのか?
関数は\(x\)と\(y\)の関係を決める「ルール」
関数の定義は、「\(x\)を一つ決めると\(y\)がただ一つに決まる対応関係」のことです。
このルールが崩れることは絶対にありません。
関数の式は、そのルールを文字で表したもの
\(y=2x\)のように、ルール(関数)を計算できる形にしたものが関数の式です。
これは\(x\)と\(y\)が常に守らなければならない等式を表しています。
ルールに従う\(x, y\)は、式に代入すると必ず等式が成立する
関数のルールに従っている\(x\)と\(y\)のペアは、その式の「正しい仲間」です。
だから、式に代入すると左辺と右辺が等しくなり、等式がぴったり成り立ちます。
| \(x\)と\(y\)のペア | 代入結果 | 成立or不成立 | 説明 |
|---|---|---|---|
| \(x=3,y=6\) | \(6=2\times 3\) \(6=6\) | 成立 | このペアはルールに従っている |
| \(x=3,y=5\) | \(5=2\times 3\) \(5=6\) | 不成立 | このペアはルールに従っていない |
だから、代入すると\(x,y\)を求められる
わかっている値を代入することで、残りの文字を「等式を成り立たせる値」として計算することができます。
この求められた値こそが、関数というルールが定めた正しい相棒の値なのです。

「関数とは何か」のイメージが掴みづらければ、こちらの記事を読んでみてください。
👉関数とは何か?関数の基本の考え方をわかりやすく解説
x・yの計算を例題で考えてみよう
例題1(\(y\)の求め方)
関数\(y=-2x\)で\(x=-2\)のときの\(y\)の値は?
【解説】
関数の式\(y=-2x\)に\(x=-2\)を代入する。
\(y=-2 \times ( -2)=4\)
例題2(\(x\)の求め方)
関数\(\displaystyle y=- \frac{1}{2} x\)で\(y=4\)のときの\(x\)の値は?
【解説】
関数の式\(\displaystyle y=- \frac{1}{2} x\)に\(y=4\)を代入する。
\(\displaystyle 4=- \frac{1}{2} x\)
\(\displaystyle – \frac{1}{2} x=4\)
\(x=-8\)
例題3(与えられた条件が文字の場合)
関数\(y=3x\)で\(x=a\)のときの\(y\)の値は?
【解説】
関数\(y=3x\)に\(x=a\)を代入する
\(y=3a\)

複雑な問題を解くときに、文字でおいて考えることがあります。
おわりに
\(x\)、\(y\)を計算するときは、関数の式に与えられた値を代入すると求めることができます。
いろいろな出題のされ方はありますが、方法は同じです。
この計算は、高校受験や、高校の学習でも、何度も繰り返し出てきます。
慣れるまで大変だとは思います。
でも、焦らず一歩ずつ確認していけば大丈夫です。
がんばってください。
【関連記事】
- 次の記事を読みたい方はこちら
グラフの意味を理解すると、グラフ上の点の求め方や、交点の求め方などの根拠がよくわらかります。
しっかり理解すると、ばらばらだった知識が一つにまとまってきますよ。
👉グラフは関数の式を満たす点の集まり!グラフの意味の理解 - 一次関数の式で\(x,y\)を求める方法を具体的に知りたい方はこちら
\(x,y\)を求めるときの、基本から押さえておきたい考え方まで解説しています。
👉x・yの計算は一次関数の式への代入!例題、間違えやすい計算、考え方まで網羅 - 関数の基本シリーズまとめに戻る方はこちら
全体の進捗を確認して、足りないところを補強していけば、関数の基礎的な力が身に付きますよ。
👉関数の基本シリーズまとめページ

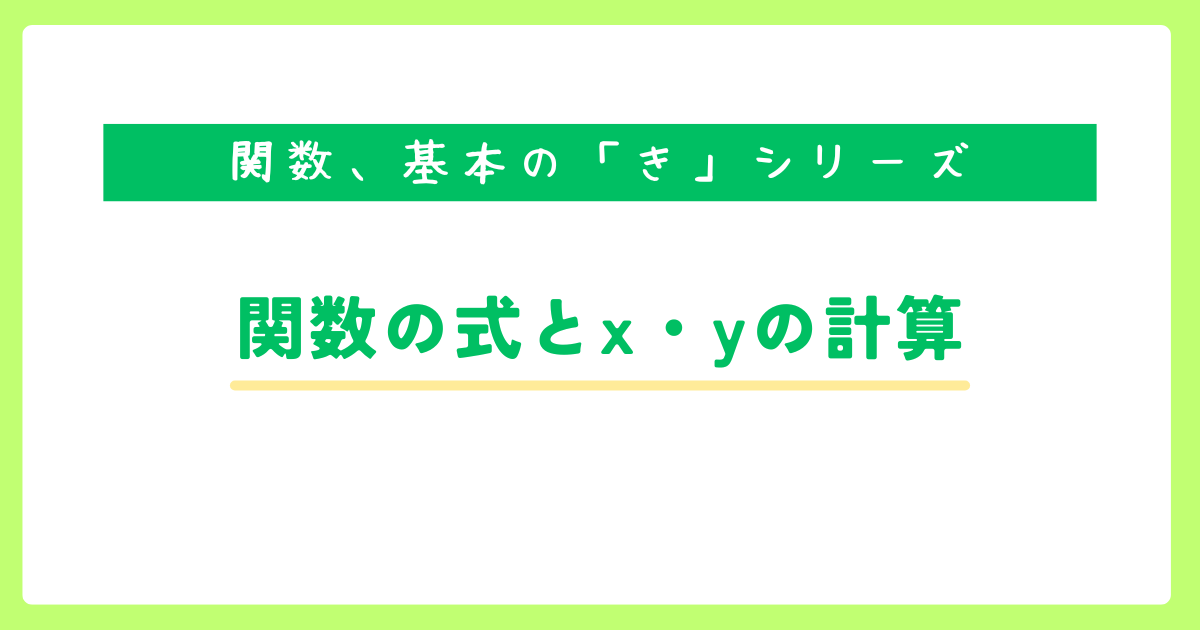
コメント