「因数分解の問題を見るたびに、どの公式を使えばいいかパニックになる……」
そんな経験はありませんか?
因数分解は、公式を5つ覚えただけでは、実は不十分。
大切なのは、それらを「どの順番で検討するか」という戦略です。
闇雲に解くのをやめて、正しい「見極め順序」を身につけるだけで、計算スピードは劇的に上がり、ミスは驚くほど減ります。
今回は、私が塾講師時代に説明していた「因数分解アルゴリズム(手順)」をお伝えします。
今日からあなたの頭の中が、驚くほどスッキリ整理されるはずです。
【4ステップ】因数分解の公式はどの順番で考えればいい?
中学校範囲の因数分解は、次のステップで考えると、漏れなく、効率的に考えることができます。
要するに
- 共通因数
- 「2乗-2乗」の公式
- 2乗の公式
- 和と積の公式
の順で検討すればよいということです。
では、次から、なぜこの順番なのかについて解説していきます。
なぜ因数分解の公式はこの順番で考えるの?
因数分解は5者択一
そもそもの話になるのですが、公式以外に因数分解をする方法はありません。
なぜなら、平たく言ってしまえば、「展開公式が成り立つんだから、その逆も成り立つでしょ」というのが因数分解だからです。
そのため、中学校範囲では
「因数分解をする」=「5つの公式の中から適切なものを選んで使う」
ということになります。
だから、公式を選ぶときは消去法で考えていくと漏れなく考えることができます。

苦手な人ほど「他に自分の知らない解き方があるのかも」と思って手が止まりがちですが、因数分解に関して言えば本当に公式以外解き方がありません。
応用問題も、結局は公式の組み合わせで解きます。
最初に共通因数を考える理由
最初に共通因数を考える理由は次の2つです。
- 後の計算が楽になる:
共通因数でくくると、カッコの中の数字が小さくなます。
そのため、公式を2回以上使う応用問題で、他の公式に気づきやすくなります。 - 見つけやすい:
各項を眺めるだけなので、脳への負荷が最も低いです。
次に「2乗-2乗」を考える理由
2番目に「2乗-2乗」を考える理由は次の2つです。
- 見つけやすい:
項の数が2つで、「2乗の公式」、「和と積の公式」より見分けがつきやすい - 忘れやすい:
他の項が3つの公式を先に検討してしまうと、頭の中の選択肢から漏れてしまいやすい
「2乗の公式」を「和と積の公式」より先に考える理由
これも見つけやすいという理由に尽きます。
「2乗の公式」が使えるかどうかは、次の2つを見れば確認できます。
- 定数項が2乗の数字か
- \(x\)の係数を見て、定数項を2乗する前の数字の2倍になっているか
2つとも、確認はほぼ見るだけになるので、「和と積の公式」に比べれば、確認ははるかに簡単です。
一番面倒なものは、一番後回し
ここまでで該当する公式がなければ、残されているのは「和と積の公式」だけです。
この公式は、他の公式よりも考えることが多いため、最後に時間をかけて検討するようにするとよいです。
公式検討の手順は、とても平たく言うと「簡単」を先、「複雑」を後に考えています。
なぜ「簡単」を先、「複雑」を後にするのか?
脳のメモリ(余裕)をイメージしてください。
たとえば、5つの選択肢が頭に残った状態だと、5つの選択肢に意識を割かないといけないので脳をフル活用できません。
検討が終わった選択肢を頭から追い出していくと、その分脳の余裕が増えて、脳を使いやすくなっていきます。
- 共通因数・2乗-2乗:
パッと見でわかる「例外」。
すぐに処理して脳から追い出せる。 - 和と積:
候補を書き出す「重い作業」。
他の可能性をすべて消してから、残った脳のパワーを全投入する。
一番処理が重い「和と積」を最後にまわしているのは、重い処理に脳をフル活用するためなんです。
この考え方は、因数分解に限った話ではありません。
消去法で選ぶときは、「考えやすい例外」から先に考えると、処理の重い思考に脳をフル活用できて、効率的に考えることができるんです。

もうちょっと付け加えると、「考えやすさ」以外に「ミスを起こしたときの重大度」も、検討の優先順位を上げます。
何かの手順を見かけたら、実は「考えやすさ」や「ミスしたときの重大度」も検討の軸としてあると知っておくと、手順に対する理解が深まりますよ。
おわりに
因数分解は、いわば「5枚のカードから正解の1枚を引くゲーム」です。
強いプレイヤーは、当てずっぽうに引くのではなく、外れやすいカードから順に捨てていくことで、確実に正解にたどり着いています。
今回紹介した「4ステップ」を意識して演習を繰り返せば、いつの間にか無意識に公式を選べるようになります。
共通因数 → 2乗-2乗 → 2乗の公式 → 和と積
この「順番」を、あなたの武器にしてくださいね。
【関連記事】
- この記事の演習記事を読まれる方はこちら
公式が選べないまま計算練習をしても、効率は上がりません。
まずは「計算を切り離して、公式を見抜く力」だけを集中的に鍛えてみませんか?
自分の考え方のクセを修正したい方は、ぜひ一度トライしてみてください。
👉因数分解の公式選択10本ノック!計算せずに「見抜く力」を鍛える特訓

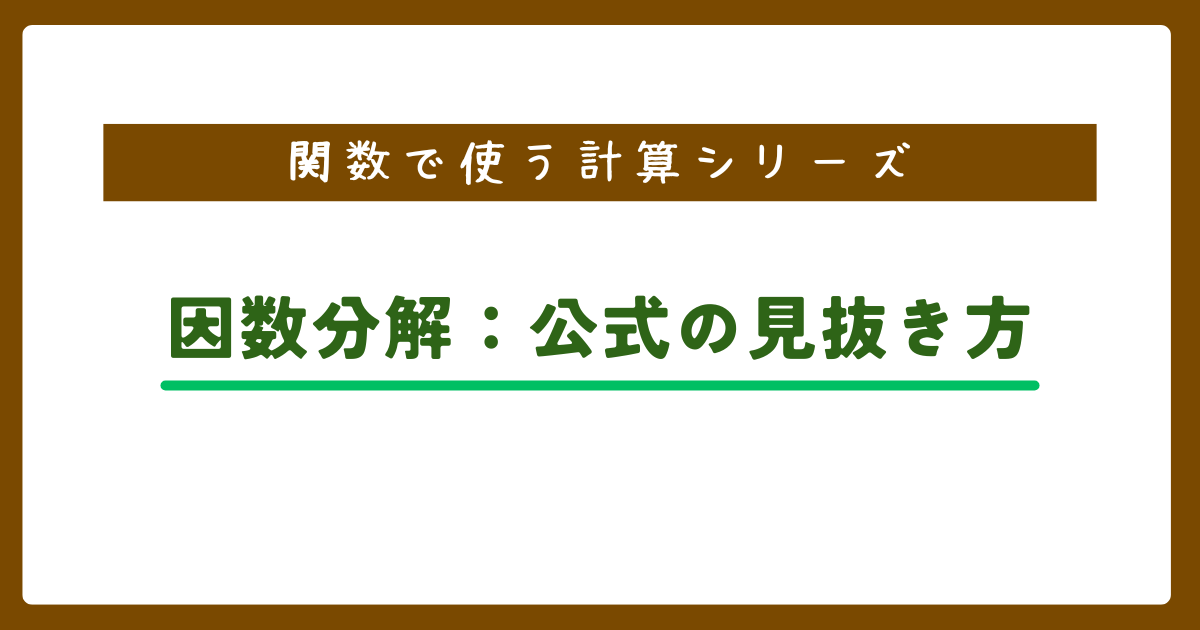
コメント