中学校で「関数」という言葉が出てくると、何となく難しそうに感じる人も多いと思います。
でも、落ち着いて考えると、実はそんなに難しくはなかったりします。
関数とは、かんたんに言えば「1つの数が決まると、もう1つの数も決まるしくみ」のことです。
たとえば、使った時間で料金が決まるコインパーキングや、歩いた距離で消費カロリーが決まるスマートウォッチなど、身のまわりにも関数の考え方はたくさんあります。
この記事では、「関数とは何か」という考え方の出発点を整理して、関数の単元でどんなことを学んでいくのかを見ていきたいと思います。
関数って何のこと?
関数は\(x\)と\(y\)の決まり方のルール
関数の意味について詳しく解説
「関数」の「関」という字で何を思い浮かべますか?
多くの人は「関係」や「関わり」といった言葉を思い浮かべると思います。
「関数」の「関」もまさにこの意味で、\(x\)と\(y\)の関係(ルール)のことです。
たとえば、「\(y\)は\(x\)を2倍したもの」というルールがあったとします。
すると、
\(x=3\)のとき\(y= 2 \times 3 = 6\)
\(x=-1\)のとき\(y= 2 \times (-1) = -2\)
のように、\(x\)を1つ決めると、\(y\)が1つに決まります。
このようなルールを関数と呼んでいるのです。

イメージとしては「工場の機械」がわかりやすいかと思います。
工場の機械では、材料を入れると、必ず決まった製品が出てきます。
同じように、関数に\(x\)を入れると、決まった\(y\)が出てくるのです。
関数はどうやって考えていくの?
「関数の式」、「グラフ」と「関数」の関係
関数(ルール)は文章で書けますが、そのままだと扱いづらいことがあります。
そこで、関数を式の形で表したものを関数の式といいます。
「\(y\)は\(x\)を2倍したもの」なら
\(y=2x\)
と表せます。
この関数の式を、「見える形」で表したのがグラフです。
式が“計算の道具”だとすれば、グラフは“イメージの道具”。
どちらも同じ関数を、ちがう角度から見ているだけです。
関数の種類にはどんなものがある?
関数には、いくつか代表的なものがあります。
中学校では「比例・反比例」「一次関数」「二次関数」を学びます。
高校ではさらに「三角関数」「指数関数」「対数関数」などへと広がっていきます。
学ぶ関数の形は変わっても、「\(x\)と\(y\)の関係を式やグラフでとらえる」という基本は同じです。
関数の勉強ではどんなことを学ぶの?
関数の学習内容を深掘り
関数の学習では、次の3つができるようになることが大きな目標です。
- その単元の関数の特徴
- 関数の式の表し方・使い方
- グラフの表し方・使い方
具体的には、
「\(x\)が〇のとき、どうやって\(y\)を求めたらよいのか」、
「一次関数のグラフはどう描けばいいのか」、
「2つのグラフが交わる点を求めるためには関数の式をどう使えばいいのか」
などといったことを学んでいくのです。

中身の関数自体が変わるだけなので、実は、単元が変わっても共通する操作がかなりあります。
だから、最初はとっつきづらいですが、一度理解してしまえば後が楽になっていきます。
おわりに
関数は、「数と数の関係」を整理して考えるための道具です。
\(x\)と\(y\)、2つの数のあいだにルールを見つけて、それを式やグラフで表し、条件に合わせて使えるようにすること。
これが中学・高校で関数を学ぶ大きな目的です。
最初は「\(x\)と\(y\)がセットで変わる」ことを意識して、「どんな決まりで変わるのか」を読み取れるようになりましょう。
【関連記事】
- 続きの記事を読みたい方はこちら
関数の式から\(x,y\)を計算する方法の論理的な根拠についてまとめました。
関数の基本計算ですが、根拠がわかれば定着もしやすいので、ぜひ読んでみてください。
👉関数の式からx・yを計算できる論理的根拠 - 一次関数とは何かを学びたい方はこちら
この記事でまとめた関数のうち、\(y\)が\(x\)の一次式で表せるものを「一次関数」と呼びます。
一次関数とは何か、どういう特徴があるのかについてまとめました。
👉一次関数とは何か?a,bの意味をわかりやすく解説 - 関数の基本シリーズまとめに戻る方はこちら
全体の進捗を確認して、足りないところを補強していけば、関数の基礎的な力が身に付きますよ。
👉関数の基本シリーズまとめページ

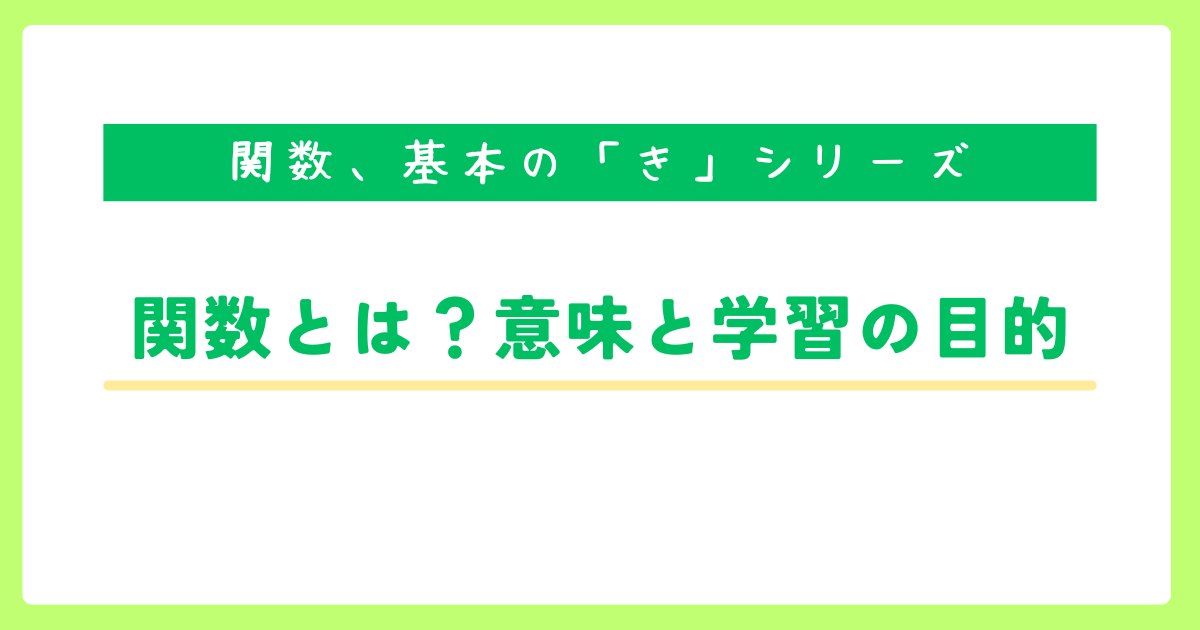
コメント
地元の自治体主催の学習支援事業にボランティアとして参加しています。
主に小、中学生が対象です。中には塾に行っている子もいますが、学校の授業について行けない子、何らかの理由で、学校以外での自習をする子などがいます。
週に一日、二時間のみの活動ですが、最近、中学三年生(高校受験生)から、数学の関数が解らないという相談を受けました。
正直、自分も中学時代は遥か前の事で、殆ど解りません。何とか分かり易く教えてあげたいと思いますが、自分の理解も危ういのに、受験生にどう教えてあげられるか正直解りません。
主催の方にも相談しましたが、自分で勉強するのがいいよといわれました。それはそうですが、その子の将来に関わる事なので、自分できちんと理解した上で、教える事が出来ればと思っています。そしてその子が、第一志望の高校に合格出来ればと思っています。良きアドバイスをお願いします。
コメントありがとうございます。
生徒さんのために、自分でもう一度勉強して教えてあげたいという気持ち、本当に素敵だと思います。
きっとその想いは、生徒さんにも伝わっていると思います。
関数は、平たく言うと「xとyの対応関係のこと」と思っていただくといいと思います。
対応の仕方によって、比例(xが〇倍になるとyも〇倍、y=ax)、反比例(xが〇倍になると、yは1/〇倍、y=a/x)、一次関数(y=ax+b)、xの2乗に比例する関数(y=ax~2)みたいに名前がついています。
そのため、まず「xとyの関係をつかむ」ことが大事です。
志望校にもよるのであまり無責任なことも言えませんが、具体的には
・関数の式を使ってx、yを計算する
・x、yから関数の式を求める
(どっちもグラフ形式での出題が多いです)
ができれば、地域のトップ校とかでなければ、関数で足を引っ張ることはないかなあという印象です。(たぶん50点満点の入試で2~4点ぐらい)
もしよければ、このブログも学習の参考にしてみてください。
まだ始めたばかりで拙いところばかりですが、「ここがわかりづらかった」「こういう説明がほしい」といったことがあれば、ぜひ教えてください。
そうした声をもとに、記事の書き直しや新しい内容の追加もしていきたいと思っています。
(仕事しながらなので更新頻度はちょっと遅いかもしれませんが)
こうして誰かの力になりたいと思ってくださる方に出会えて、本当にうれしいです。
また何かありましたら、お気軽にコメントください。