「変化の割合の計算、いまいち整理できない」
そんなふうに感じたことはありませんか?
変化の割合の計算では、「変化前」と「変化後」を整理して、それぞれの増加量を求める必要があります。
やることが意外と多く、頭の中だけで考えると混乱してしまうこともありますよね。
こうした“前後の値を比べる”タイプの問題では、表を使って整理するとスッキリ解けることが多いです。
この記事では、変化の割合の問題を表で整理する方法を、例題付きでわかりやすく解説します。
【関連記事】
- 変化の割合やその公式の意味に自信がない方はこちら
変化の割合は、意味と考え方がわかれば、公式を覚えなくても大丈夫です。
詳しくはこちらの記事で解説しているので、変化の割合に苦手意識のある方は、まずこちらの記事をお読みください。
👉意味を理解して脱暗記!変化の割合の意味と公式
変化の割合の意味と公式(前提知識の確認)
変化の割合は\(x\)の増加量に対する\(y\)の増加量の割合のこと
この知識を使って、問題を考えていきます。
変化の割合の計算って表を使ったらどうやって整理できる?
変化の割合の表を使った整理の手順
変化の割合の表を使った整理方法を具体例で確認
変化の割合の問題では、表を使って\(x\)と\(y\)の変化前・変化後を整理すると分かりやすいです。
たとえば、点(-1, 13)から点(4, 3)に変化したときの変化の割合を計算する場合を考えます。
まず、横の行に\(x\)、\(y\)、縦の列に変化前、変化後、増加量を書いた表を作成します。
(下図参照)
| 変化前 | 変化後 | 増加量 | |
|---|---|---|---|
| \(x\): | -1 | 4 | 5 |
| \(y\): | 13 | 3 | -10 |
次に、この表に与えられた条件を書き入れます。
変化前の点が(-1, 13)
⇒変化前の\(x=-1、y=13\)
変化後の点が(4, 3)
⇒変化後の\(x=4、y=3\)
なので、条件を書きこむと下図のようになります。
| 変化前 | 変化後 | 増加量 | |
|---|---|---|---|
| \(x\): | -1 | 4 | |
| \(y\): | 13 | 3 |
次に、増加量を計算します。
増加量の値は(変化後の値)-(変化前の値)です。
\(x\)の増加量:
4-(-1)=5
\(y\)の増加量:
3-13=-10

符号を考えて、引く順番を変えようとする人がときどきいますが、混乱のもとになるので、「後-前」で徹底してください。
| 変化前 | 変化後 | 増加量 | |
|---|---|---|---|
| \(x\): | -1 | 4 | 5 |
| \(y\): | 13 | 3 | -10 |
よって、変化の割合は
-10 ÷ 5 = -2

変化の割合に限らず、何かを比較したいときは、表を使うととても考えやすくなりますよ。
変化の割合の求め方を例題で解説
例題1(増加量を計算して変化の割合を求める)
点(3, 6)から点(1, 12)に変化したときの変化の割合は?
【解説】
\(x\)、\(y\)の表を作成すると、下図のようになる。
| 変化前 | 変化後 | 変化の割合 | |
|---|---|---|---|
| \(x\): | 3 | 1 | -2 (=1-3) |
| \(y\): | 6 | 12 | 6 (=12-6) |
変化の割合は
6 ÷ (-2) = -3
例題2(一次関数の変化の割合を求める問題)
一次関数\(y=2x-3\)において、\(x\)が-1から4まで増加するときの変化の割合は?
【解説】
例題1と違い、例題2では\(x\)の値しかわかっていません。
そのため、まず\(y\)の値を計算する必要があります。
\(x=-1\)を\(y=2x-3\)に代入して
\(y=2 \times (-1) -3 =-5\)
\(x=4\)を\(y=2x-3\)に代入して
\(y=2 \times 4 -3 =5\)
| 変化前 | 変化後 | 増加量 | |
|---|---|---|---|
| \(x\): | -1 | 4 | 5 (=4-(-1)) |
| \(y\): | -5 | 5 | 10 (=5-(-5)) |
変化の割合は
10 ÷ 5 = 2
変化の割合の計算の思考ロジック
「変化の割合の計算⇒\(x,y\)の増加量が必要⇒\(x,y\)の計算が必要」という考え方を身に付けてください。
特に例題2のような問題では、考える量が多く、求めたいものから逆算しないと、方針が決まりにくいです。
解説を読んで、「書いてあることはわかるけど、自分では解けない」という方は、おそらく考え方の順序が身についていないのだと思います。

こちらの記事で、変化の割合の問題を考える順序についてまとめています。
どう考えるか、どこから考えるかについて詳しくまとめたので、ぜひ読んでみてください。
👉もう迷わない!逆算思考で考える変化の割合の計算順序
おわりに
今回は、「変化の割合」を表で整理しながら考える方法について解説しました。
最初は少し難しく感じるかもしれませんが、考える順番を身につけて、表を使って条件を整理できるようになれば、必ず解けるようになります。
「どの数どうしを比べればいいのか」を意識できるようになると、計算の意味もはっきりして、問題の見通しがぐっとよくなります。
また、表で前後の変化を比べる力は、数学だけでなく、いろいろな場面で役に立ちます。
焦らずに、まずは1つ1つの考え方を丁寧に整理していきましょう。
少しずつでも確実に、考える力がついていきます。
【関連記事】
- 次の解説記事を読みたい方はこちら
一次関数のグラフで、傾き、切片がグラフ上での役割についてまとめました。
一次関数のグラフの読み描きの基本になるので、ぜひ読んでみてください。
👉一次関数のグラフ!傾きa、切片bのグラフ上での役割を知ろう - 演習をして変化の割合の計算方法を定着させたい方はこちら
一次関数の単元での変化の割合の演習問題の演習記事です。
基本的な公式確認の問題から、一次関数の中で、\(y\)の値、\(x,y\)の増加量を求める問題まで、幅広く解説しています。
知識を定着させたい方はぜひお読みください。
👉【レベル別演習】一次関数の変化の割合の求め方と表を使った計算の工夫 - 変化の割合の計算の順序について詳しく知りたい方はこちら
こちらの記事で、変化の割合の問題を考える順序についてまとめています。
どう考えるか、どこから考えるかについて詳しくまとめたので、ぜひ読んでみてください。
👉もう迷わない!逆算思考で考える変化の割合の計算順序 - 一次関数のまとめに戻る方はこちら
関数は、抽象的で取り組みづらい反面、同じ操作が繰り返し出てくるので、コツが掴めると得意にしやすい分野でもあります。
考え方からていねいに解説しているので、ぜひ先々まで活用できるかたちで知識を身に付けてください。
👉【完全攻略】一次関数の解き方・考え方を基礎からじっくり

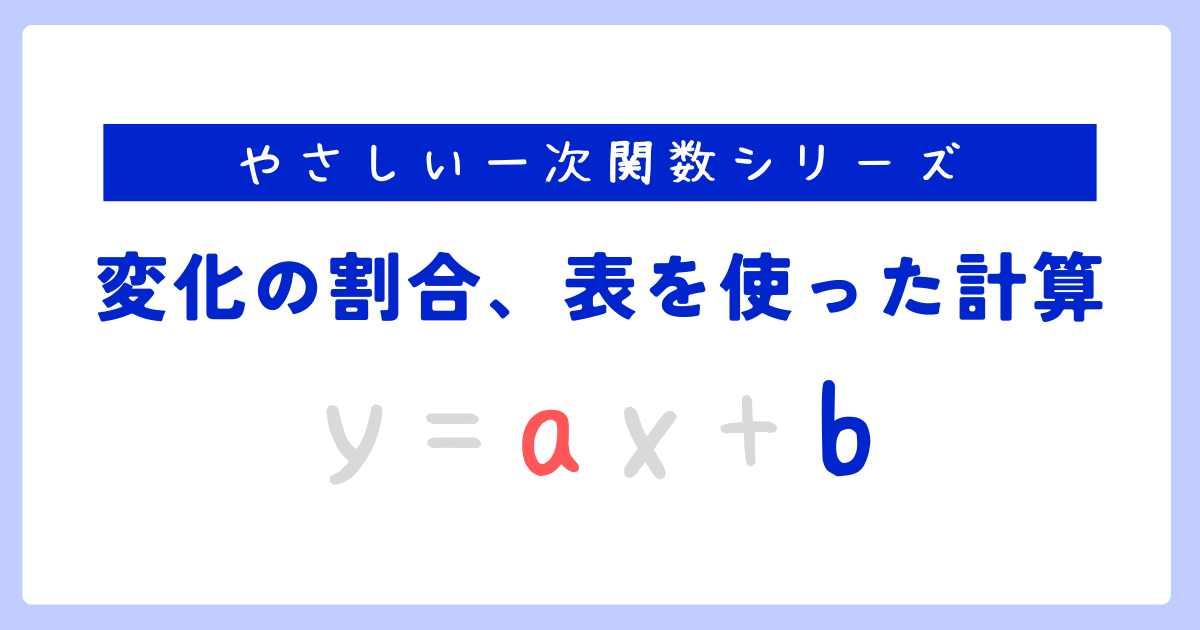
コメント