「変化の割合、解説を読めばわかるのに、自分で解くとなると手が止まる。」
そんな経験はありませんか?
中2数学で学ぶ変化の割合は、計算手順が多く、「どこから手をつけたらいいのか」迷いやすい単元です。
この記事では、変化の割合を「逆算思考」で整理する方法を紹介します。
求めたいものを出発点にして考えることで、計算の順序がわかりやすくなり、定期テストや高校入試でも迷わず手を動かせるようになります。
例題を使って、思考の流れを一緒に確認していきましょう。
変化の割合の問題はどこから考え始めればいい?
変化の割合は、「求め方」から逆算していく
変化の割合を考えるときは、次の順の思考を踏むとうまくいくことが多いです。
変化の割合の計算での逆算の考え方を詳しく解説
逆算の考え方って何?
逆算の考え方とは、条件からではなく、求めたいものをスタートにして条件にさかのぼっていく考え方のことです。
公式を1回使えば答えが出るような基本問題では、条件から読んでも特に問題はありません。
しかし、条件や、計算過程が増えると、何をどこから使っていいかが整理できなくなってしまいます。
こういうときに効くのが、”逆算の考え方”です。
「求めたいもの」を出発点にして方針を考えると、条件から考えるよりも、思考の整理がスムーズにできます。

逆算の考え方の基本については、こちらの記事で解説しています。
理解を深めたい方はぜひお読みください。
👉解説はわかるのに解けない?数学で大切な逆算の考え方
具体的に、変化の割合の計算ではどうやって使ったらいい?
まず、変化の割合の計算手順を思い出してください。
すると、\(x\)、\(y\)の増加量がわからないと、計算できないとわかります。
さらに、\(x\)、\(y\)の増加量を計算するためには、それぞれの点の\(x\)座標、\(y\)座標が必要なことがわかります。
\(x\)座標、\(y\)座標を求めるためには、関数の式と、\(x\)座標または\(y\)座標が必要です。
ここまで思考が整理できたら、そこで改めて問題文の条件を見ると、解答の方針が見えてくると思います。

変化の割合の計算方法や、関数の式から\(x,y\)を計算する方法に自信のない方は、こちらの記事をお読みください。
- 変化の割合の意味、計算方法
👉変化の割合とは?公式の意味を例題付きでくわしく解説 - 関数の式から座標を求める方法
👉関数の基本操作!関数の式から座標を求める方法
逆算思考での変化の割合の考え方を例題で見てみよう
例題1(一次関数の変化の割合を求める問題)
一次関数\(y=2x-3\)において、\(x\)が-1から4まで増加するときの変化の割合は?
【解説】
変化の割合をスタートにして考えると
- (変化の割合)=(\(x\)の増加量)÷(\(y\)の増加量\)
- \(x\)、\(y\)の増加量が必要
- \(x\)座標、\(y\)座標が必要
⇒条件から関数の式と\(x\)座標はわかる
⇒\(y\)座標を計算
これを逆にたどっていくと
- \(x=-1\)のとき\(y=-5\)
\(x=4\)のとき\(y=5\) - \((xの増加量)=4-(-1)=5\)
\((yの増加量)=5-(-5)=10\) - (変化の割合)=10 ÷ 5 = 2
と計算できます。

例題2は中3の内容も混じっているので、未習の人は飛ばしてもらって大丈夫です。
例題2(一次関数以外の変化の割合、文字が入った場合)
2次関数\(y=ax^2\)において、\(x\)が-2から1に変化するときの変化の割合が3である。
\(a\)の値を求めなさい。
直接、「変化の割合を求めなさい」と問われているわけではないですが、これも変化の割合をスタートにすると考えやすくなります。
- (変化の割合)=(\(x\)の増加量)÷(\(y\)の増加量\)
- \(x\)、\(y\)の増加量が必要
- \(x\)座標、\(y\)座標が必要
⇒条件から関数の式と\(x\)座標はわかる
⇒\(y\)座標を計算
これを逆にたどっていくと
- \(x=-2\)のとき\(y=4a\)
\(x=1\)のとき\(y=a\) - \((xの増加量)=1-(-2)=3\)
\((yの増加量)=a-4a=-3a\) - \((変化の割合)=-3a \div 3 =-a \)
条件から、変化の割合は3なので
\(-a=3\)
\(a=-3\)

話が逸れるので省略しましたが、増加量の整理にとまどうときは表を使った整理方法が効果的です。
詳しい方法については、こちらのお読みください。
👉一次関数、変化の割合の計算!表を使った計算の工夫
おわりに
この記事では、変化の割合の問題を考え方の順序に焦点を合わせて整理しました。
教科書にも出てくる基本問題なので、結構スルーされがちですが、複雑な問題を順序だてて考える練習をするのに、ちょうどいい問題だと個人的には思っています。
どこから考え始めたか、どういうプロセスを踏んだかをしっかり理解して取り組むと、間違いなく自分の力になる問題です。
がんばってください。

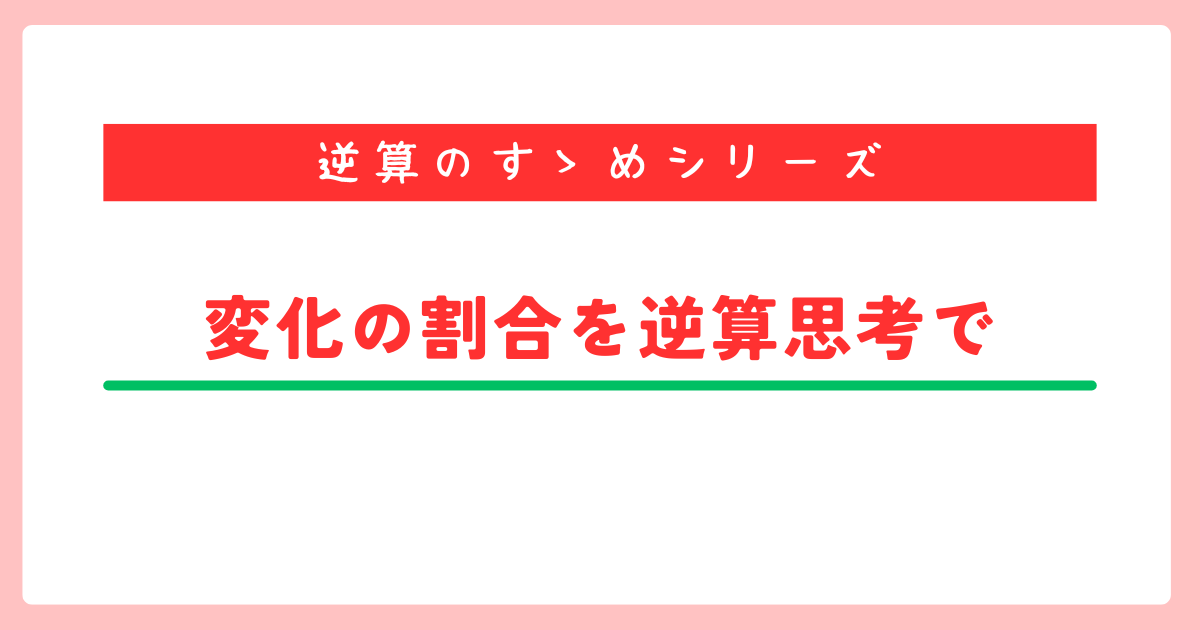
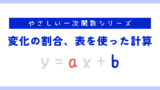
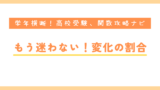
コメント