「変化の割合って何?」
そんなことを思っていないですか?
変化の割合は、公式自体はシンプルでわかりやすいです。
しかし、何をやっているのかがいまいちつかみづらくて、定期テストが終わるとすぐに忘れてしまいがちな知識です。
しかし、変化の割合は意味さえしっかりわかれば、知識はなかなか抜けません。
だから、しっかり意味を理解することが大切です。
段階的な例題と、具体的な解き方付きで、できるだけ詳しく解説しています。
よかったら読んでみてください。
【関連記事】
- 変化の割合の意味はばっちりという方はこちら
一次関数の変化の割合を計算するときに、間違えやすいのが増加量の計算。
こういうときは、表を使って整理すると考えやすいです。
どうやって表を使うのか、例題付きで解説していますので、ぜひ読んでみてください。
👉変化の割合を確実に計算するためのテクニック!表の活用方法
変化の割合って何?
変化の割合について詳しく解説
変化の割合の定義は、「\(x\)の増加量に対する\(y\)の増加量の割合」のことです。
ただ、この言い方だと、少しぴんと来ないかもしれません。
「割合」という言葉は、全体に対してそれがどのくらいの分量を占めるかを表しています。
つまり、
「〇に対する△の割合」
=「〇を1としたときの△の量」
=「〇が1あたりの△の量」
と読み替えることができます。
これを変化の割合の定義に当てはめると、
「\(x\)が1増えたときに\(y\)がどれだけ増えたかのこと」
という意味になるのです。
変化の割合ってどうやって計算したらいい?
変化の割合は「\(x\)の増加量1あたりの\(y\)の増加量」のことなので、\(y\)の増加量を\(x\)の増加量で割れば求められます。
後から説明しますが、変化の割合の意味さえわかってしまえば、この公式をわざわざ覚える必要はありません。

ここから、難易度別の例題で、変化の割合の意味を確認していきます。
変化の割合|求め方を例題で解説
すごく簡単な例|変化の割合の意味の確認
まず、すごく簡単な例題で、定義の意味を確認してみましょう。
例題1(変化の割合の意味の確認)
\(x\)が1増えたとき、\(y\)が3増えた。
変化の割合は?
【解説】
定義通り考えればよいです。
変化の割合は3
例題2(変化の割合の意味の確認)
\(x\)が1増えたとき、\(y\)が2減りました。
変化の割合は?
【解説】
\(y\)が2減った
→\(y\)が-2増えたと考えて
変化の割合は-2
ちょっと簡単な例|増加量を使った言い換え
例題1、2では「\(x\)が1増えたとき」という言い方をしていました。
これを「増加量」という言葉を使って言い換えます。
- 「\(x\)が1増えたとき」
→「\(x\)の増加量が1のとき」 - 「\(y\)が2減った」
→「\(y\)の増加量が-2」
たとえば、例題2を言い換えると
\(x\)の増加量が1のとき、\(y\)の増加量は-2であった。
変化の割合は?
という問題に変わります。
もちろん答えは変わりません。
ほんのちょっと簡単な例|公式の意味と割り算
次は、公式の意味を確認してみます。
まず、変化の割合とは関係ない問題を見てみます。
例題3(合計金額とりんごの個数からりんご1個の値段を求める問題)
買い物をしています。
りんごを3個買ったら合計金額が180円増えました。
りんご1個の値段は?
【解説】
りんご3個で180円なので、りんご1個あたりを求めればよいです。
180 ÷ 3 = 60
よって、りんご1個の値段は60円
変化の割合の問題に戻ります。
例題4(増加量から変化の割合を計算)
\(x\)の増加量が3のとき、\(y\)の増加量は180です。
変化の割合は?
【解説】
\(x\)が3増加したら\(y\)が180増えているので、\(x\)の増加量が1あたりでは
180 ÷ 3 = 60
よって、変化の割合は60

\(\displaystyle 180 \div 3 = \frac{180}{3}\)
と考えれば、計算は公式の形になっています。

例題3、4を比べると、計算がまったく同じです。
これは、偶然でも何でもありません。
例題3を難しく言い返ると
りんごの増加量1個あたりの合計金額の増加量
を求めていると言えます。
一方、変化の割合とは
\(x\)の増加量1あたりの\(y\)の増加量
のことです。
つまり、例題3、4は同じことを求めているのです。

りんご1個の値段を計算するのに公式を覚える必要はないですよね?
同じように、変化の割合は、意味さえわかってしまえば、公式を覚えていなくても計算できるんです。
おわりに
変化の割合は、公式を覚えるための知識ではなく、「変わり方の大きさ」を考えるための考え方です。
ここで学んだ「\(x\)が1増えたときに、\(y\)がどれだけ増えるか」という考え方をしっかりつかんでおけば、一次関数の「傾き」や「グラフの読み取り」にそのままつながっていきます。
最初は、なかなか定着しづらいかもしれませんが、何度も繰り返すと感覚的につかめるようになってきます。
がんばってください。
【関連記事】
- 次の解説記事を読む方はこちら
準備中です。すみません。 - 一次関数の単元での変化の割合についての記事を読みたい方はこちら
一次関数の変化の割合を計算するときに、間違えやすいのが増加量の計算。
こういうときは、表を使って整理すると考えやすいです。
どうやって表を使うのか、例題付きで解説していますので、ぜひ読んでみてください。
👉変化の割合を確実に計算するためのテクニック!表の活用方法 - 一次関数の変化の割合の計算を練習したい方はこちら
一次関数の単元での変化の割合の演習問題の演習記事です。
基本的な公式確認の問題から、一次関数の中で、\(y\)の値、\(x,y\)の増加量を求める問題まで、幅広く解説しています。
知識を定着させたい方はぜひお読みください。
👉【レベル別演習】一次関数の変化の割合の求め方と表を使った計算の工夫

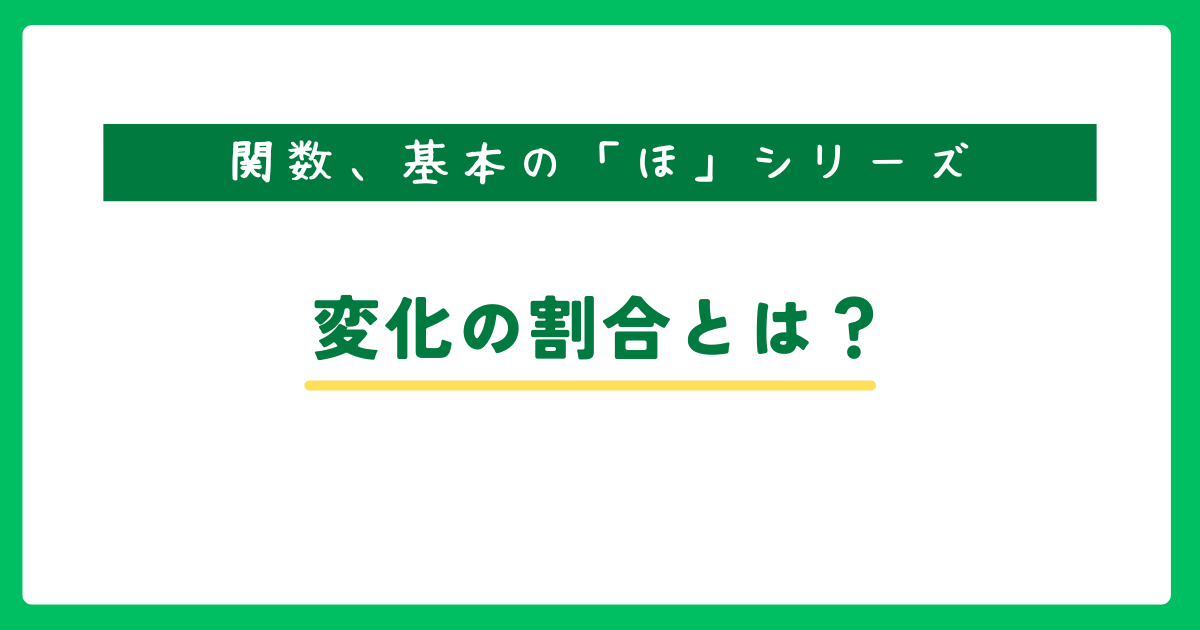
コメント