一次関数の定期テストでは、ほぼ必ず出てくる「変化の割合」。
でも、いざ練習しようと思っても、ちょうどいいレベルの問題って意外と少ないんですよね。
変化の割合は、\(x\)と\(y\)の増え方の関係を考える大事なポイント。
けれど最初のうちは、どこから手をつければいいのか分かりにくい単元でもあります。
そこで今回は、変化の割合を段階別に練習できるようにまとめました。
苦手な人でも、ステップを踏んで理解できるようになっています。
【関連記事】
- 変化の割合やその公式の意味に自信がない方はこちら
変化の割合は、意味と考え方がわかれば、公式を覚えなくても大丈夫です。
詳しくはこちらの記事で解説しているので、変化の割合に苦手意識のある方は、まずこちらの記事をお読みください。
👉意味を理解して脱暗記!変化の割合の意味と公式 - 変化の割合の計算の工夫について自信のない方はこちら
変化の割合の計算方法について、確実に考えられる表を使った計算の工夫についてまとめています。
変化の割合が苦手という方はぜひ読んでみてください。
👉一次関数の変化の割合!確実に計算するための表を使った工夫
変化の割合を求めるための計算
解き方のポイント
変化の割合を計算するときは、次の3つを押さえると考えやすいです。
解説
それぞれのポイントについて簡単に解説します。
変化の割合の計算方法
一応、公式扱いになっていますが、変化の割合の意味がわかっていれば、公式として暗記する必要はありません。
詳しくはこちらの記事で解説しているので、気になったらお読みください。
👉変化の割合とは?公式の意味を例題付きでくわしく解説
増加量の計算
増加量の計算は、「後-前」で計算できます。
よくミスする計算なので、必ずこの順番で計算するようにしてください。
特に見かけるミスは次の2つです。
引く順番を変えてしまう
特に「小さい方から大きい方を引くとき」にやりがちです。
たとえば、\(y\)の値が 5→2に変化するときの\(y\)の増加量の、
正しい計算とよくある間違いは次のようになります。
- 正)
2-5 = -3 - 誤)
5-2 = 3
負の数の引き算を間違える
負の数を扱うときは、数字全体にカッコをつけると間違いにくくなります。
たとえば、\(y\)の値が -3→-1に変化するときの\(y\)の増加量の、
正しい計算とよくある間違いは次のようになります。
- 正)
(-1)-(-3)
=-1+ 3
= 2 - 誤)
-1-3 =-4
増加量の計算が必要な問題では、表を描いて整理する
前後の比較をするときは、表を書くとうまく変化を整理することができます。
表をつかった考え方について詳しく知りたいときは、次の記事をお読みください。
👉一次関数、変化の割合の計算!表を使った計算の工夫

ここまでで計算の基本を確認できました。
では実際に、問題を使って「変化の割合」を練習してみましょう。
一次関数|変化の割合の演習
変化の割合の計算方法の確認
演習1
\(x\)の増加量が4のとき、\(y\)の増加量は-12であった。
変化の割合を求めなさい。
解説
\(x\)の増加量1あたりの\(y\)の増加量が変化の割合なので
\(y\)の増加量を\(x\)の増加量で割れば、変化の割合を計算できる。
\( \text{変化の割合}=(-12) \div 4 =-3\)
演習2
変化の割合が-3である。
\(x\)の増加量が2のときの、\(y\)の増加量を求めなさい。
解説
\(x\)が1増加したときの\(y\)の増加量が変化の割合なので
変化の割合に\(x\)の増加量をかけると\(y\)の増加量を計算できる。
\( \text{yの増加量}=(-3) \times 2 =-6\)
増加量の計算が必要な問題
演習3
点(1, 5)から点(4, 7)に変化したときの変化の割合を求めなさい。
解説
変化前後の\(x\)、\(y\)の表を書いて考える。
| 変化前 | 変化後 | 増加量 | |
|---|---|---|---|
| \(x\) | 1 | 4 | 3 (=4-1) |
| \(y\) | 5 | 7 | 2 (=7-5) |
\( \displaystyle \text{変化の割合}=2 \div 3 =\frac{2}{3} \)
演習4
点(-2, -1)から点(1, -10)に変化したときの変化の割合を求めなさい。
解説
変化前後の\(x\)、\(y\)の表を書いて考える。
| 変化前 | 変化後 | 増加量 | |
|---|---|---|---|
| \(x\) | -2 | 1 | 3 (=1-(-2)) |
| \(y\) | -1 | -10 | -9 (=(-10)-(-1)) |
\( \displaystyle \text{変化の割合}=-9 \div 3 = -3 \)
x,yの計算が必要な問題
演習5
一次関数\(y=4x-1\)について、\(x\)の値が2から5に変化するとき、それぞれ次の値を求めなさい。
1)\(x\)の増加量
2)\(y\)の増加量
3)変化の割合
解説
1)
「後-前」で考える。
5-2 = 3
2)
\(y\)の増加量を計算するためには、\(x\)の値に対応する\(y\)の値が必要
\(x\)=2のとき\(y\)=7
\(x\)=5のとき\(y\)=19
よって\(y\)の増加量は
19-7=12
3)
変化前後の\(x\)、\(y\)の表を書いて考える。
| 変化前 | 変化後 | 増加量 | |
|---|---|---|---|
| \(x\) | 2 | 5 | 3 (=5-2)) |
| \(y\) | 7 | 19 | 12 (=19-7) |
\( \displaystyle \text{変化の割合}=12 \div 3 = 4 \)

解説を読んだらわかるけど、自分では手が動かないという人は、考える順番の問題かもしれません。
詳しくはこちらでまとめてあるので、読んでみてください。
👉もう迷わない!逆算思考で考える変化の割合の計算順序
おわりに
今回の記事は、変化の割合を段階別に練習できるようにまとめた演習の記事でした。
一次関数の変化の割合は、中2数学で特に重要な範囲です。
変化の割合の意味をしっかりわかって、表をつかって、前後の値や増加量を整理できるようになれば、変化の割合が計算できるようになります。
何度か繰り返せば、解き方も身についてきます。
がんばってください。
【関連記事】
- 次の解説記事を読みたい方はこちら
一次関数のグラフで、傾き、切片がグラフ上でどういう役割を果たすのかについてまとめました。
一次関数のグラフの読み描きの基本になるので、ぜひ読んでみてください。
👉一次関数のグラフ!傾きa、切片bのグラフ上での役割を知ろう - 次の演習記事を読みたい方はこちら
整数・分数どちらのタイプもふくめて、一次関数のグラフを実際に描いて練習できる演習記事です。
👉一次関数のグラフ:描き方の演習 - この範囲の解説記事を読みたい方はこちら
変化の割合の計算の工夫についてまとめました。
👉一次関数、変化の割合の計算!表を使った計算の工夫 - 変化の割合の計算の順序について詳しく知りたい方はこちら
こちらの記事で、変化の割合の問題を考える順序についてまとめています。
どう考えるか、どこから考えるかについて詳しくまとめたので、ぜひ読んでみてください。
👉もう迷わない!逆算思考で考える変化の割合の計算順序 - 一次関数のまとめに戻る方はこちら
関数は、抽象的で取り組みづらい反面、同じ操作が繰り返し出てくるので、コツが掴めると得意にしやすい分野でもあります。
考え方からていねいに解説しているので、ぜひ先々まで活用できるかたちで知識を身に付けてください。
👉【完全攻略】一次関数の解き方・考え方を基礎からじっくり

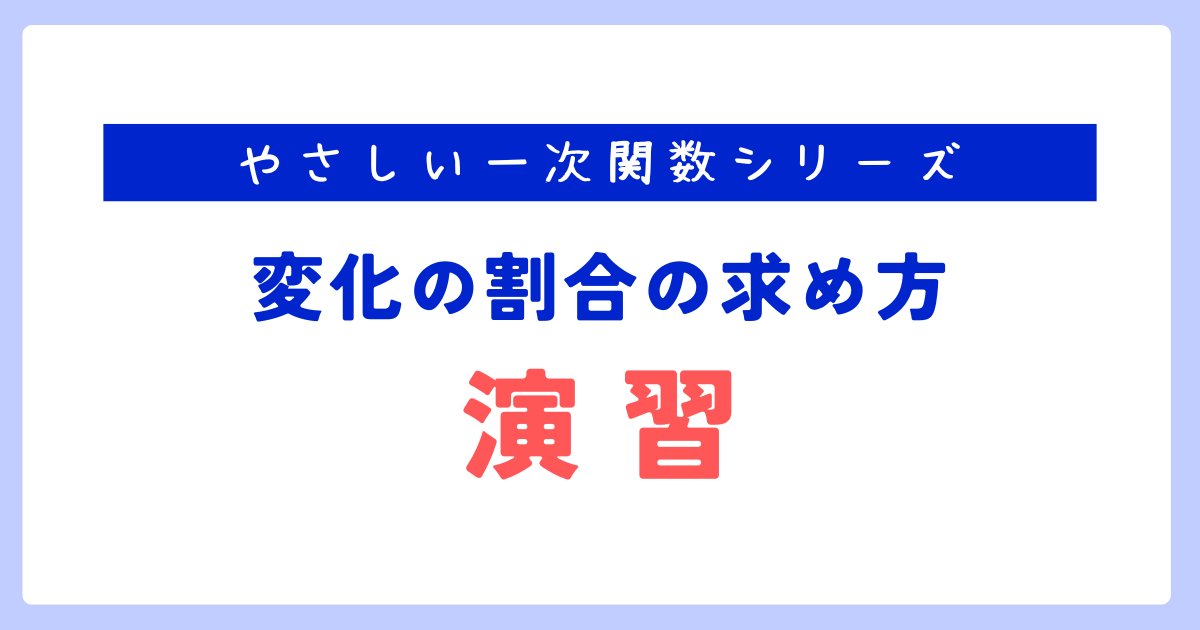
コメント