「一次関数って何?」
「\(y=ax+b\)の\(a\)や\(b\)の意味がよくわからない…」
と悩んでいませんか?
定期テストで確実に点数を取るためには、一次関数の基本を理解することが不可欠です。
この記事では、中学2年生が学ぶ一次関数「$(y=ax+b\)」を徹底解説します。
関数の意味から、\(a\)(傾き・変化の割合)と\(b\)(切片)の持つ役割まで、
例を通して分かりやすく解説します。
一次関数って何?
一次関数の意味を具体例で解説
関数って何?
関数とは、「\(x\)を1つ決めると、それに対応して\(y\)が1つに決まるときのルール(きまり)」のことです。
また、関数を式として表したものが関数の式です。
「\(x\)と\(y\)の関係を数式で書いたもの」と考えるとわかりやすいと思います。

「関数」のイメージがわかりにくい場合は、こちらの記事をお読みください。
学習することのイメージがはっきりすれば、学習効率も上がりますよ。
👉関数とは何か?関数の基本の考え方をわかりやすく解説
一次関数について具体例で解説
関数のうち、\(y\)が\(x\)の一次式(\(x\)が1乗で出てくる式)で表される関数を一次関数と呼びます。
たとえば、すでに15L入っている水槽に、1分間に2Lずつ水が増えていくときを考えてみます。
\(x\)分後の水槽の水の量を\(y\)Lとすると、
\(x\)と\(y\)について等式を立てると
\(y=2 \times x +15\)
\(y=2x+15\)
と表せます。
このように、\(y\)が\(x\)の一次式になっている関数を、一次関数と呼んでいるのです。
この式の\(x\)の係数、定数項をそれぞれ\(a\)、\(b\)で置き換えると、どんな値にもあてはまる形になります。
\(y=ax+b\)
この式が、一次関数の関数の式の一般形です。
一次関数\(y=ax+b\)の\(a,b\)ってどういう意味?
一次関数\(a,b\)の意味をくわしく解説
水槽の例を、もう一度考えてみます。
\(y=2x+15\)
の式で、\(x\)の係数2は、「1分あたりに増える水の量」でした。
もともと、水の量が\(y\)L、経過時間が\(x\)と考えています。
つまり、\(x\)が\(1\)増加すると、\(y\)は\(2(=a)\)増加します。
このように、\(a\)は「\(x\)が\(1\)増えたときに、\(y\)がどれだけ変わるか」を表しています。
一方、定数項 15 は、初めに水槽に入っている水の量でした。
言い換えると\(x=0\) のときの水の量と言えます。
つまり、\(b=15\) は「\(x\)が0のときの\(y\)の値」 を表しているのです。

このように、\(a\)や\(b\)には具体的な意味がありますが、グラフを描く際には特別な呼び方があります。
\(b\)は、\(x=0\)のときの\(y\)の値、つまりグラフが\(y\)軸と交わる点であり、切片(せっぺん)と呼ばれます。
\(a\)は、\(x\)の増加に対する\(y\)の変化の割合を表すため、変化の割合、またはグラフの傾きと呼ばれます。
補足:一次関数と比例の関係
比例の式は\(y=ax\)と表されました。
一次関数の式\(y=ax+b\)の\(b\)に0を代入すると
\(y=ax\)となり、比例の式と同じになります。
このことから、比例は一次関数の特別な形で、初めの値(\(b\))が0である特別な場合ということがわかります。
おわりに
この記事では、一次関数は\(y=ax+b\)で表される関数であること、またその\(a\)や\(b\)の意味について解説しました。
丸暗記する必要はありませんが、「なんとなくイメージできる」ぐらいにしておくと、このあとグラフを見るときに、とても理解しやすくなります。
がんばって、整理してみてください。
【関連記事】
- 続きの解説記事を読みたい方はこちら
関数の基本になる、\(x,y\)の計算方法についての解説記事です。
一次関数の、ほとんどの範囲で必要になる計算なので、しっかりマスターしてください。
👉x・yの求め方は一次関数の式に代入!計算方法と基本の考え方を解説 - 「そもそも関数って何?」と思う方はこちら
関数の意味や、関数の式、グラフと関数の関係について解説しました。
この範囲がわかると、関数で学習することの全体像が見えやすくなるので、
ぜひ読んでみてください。
👉関数とはxとyの関係!具体例で見る関数の意味 - 一次関数のまとめに戻る方はこちら
関数は、抽象的で取り組みづらい反面、同じ操作が繰り返し出てくるので、コツが掴めると得意にしやすい分野でもあります。
考え方からていねいに解説しているので、ぜひ先々まで活用できるかたちで知識を身に付けてください。
👉【完全攻略】一次関数の解き方・考え方を基礎からじっくり

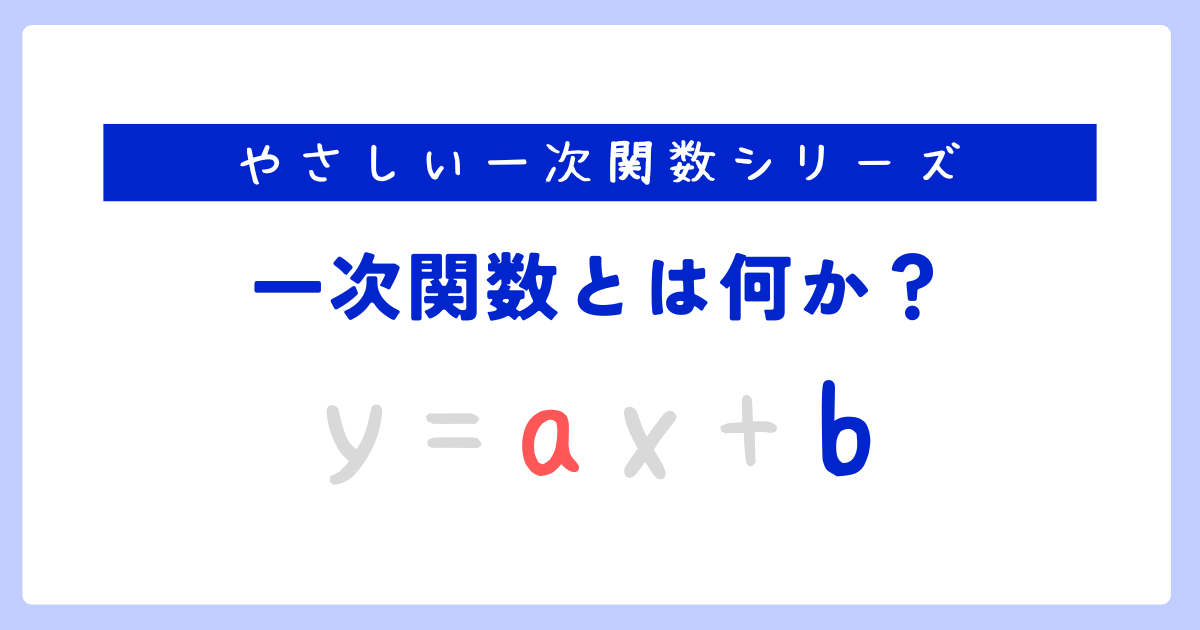
コメント